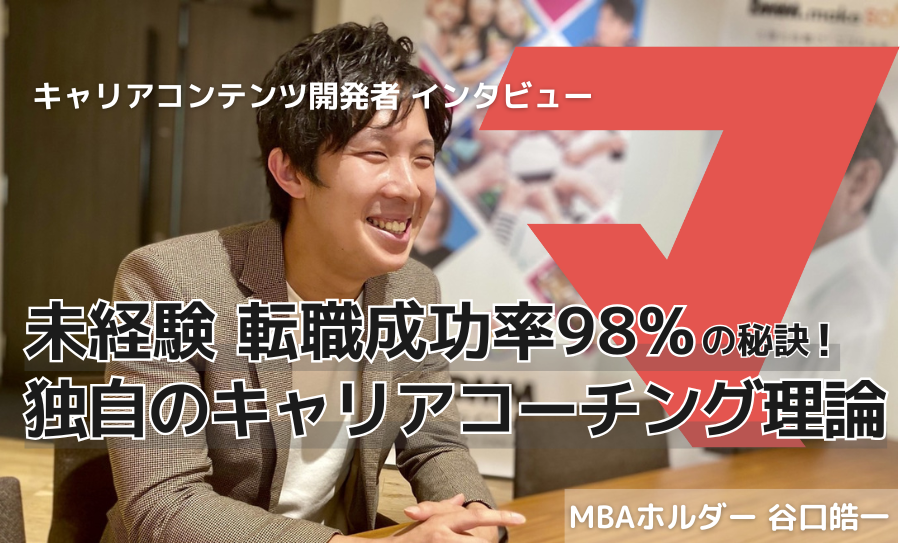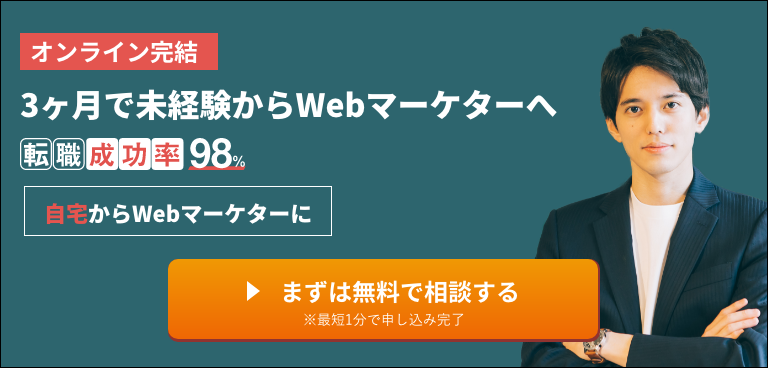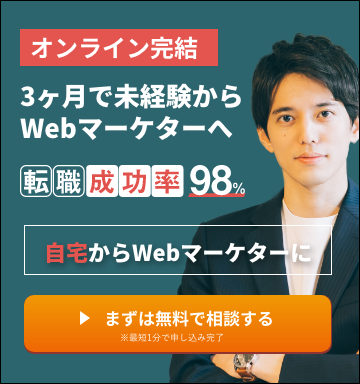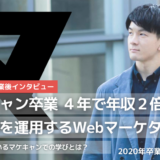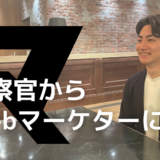本日は、これまでマケキャンにてキャリア責任者を務め、現在は社長室にて経営・事業推進を担当している谷口さんに、「マケキャン独自のキャリアコーチング理論とは」というテーマで、キャリアに対する考え方やマケキャン転職サポートの特徴など、赤裸々に語っていただきました。
現在「将来のキャリアに漠然とした不安がある」「転職はしたいけど、進むべき道がわからない」というお気持ちの方は、是非参考にしてみてください。
マケキャン 社長室:谷口 皓一 (たにぐち こういち)

グローバルヘッドハンターとして国内外の転職者支援/企業採用支援/マネジメントを経験。 ミッドキャリア〜CXOの支援までを得意とし、外資系キャリアセミナーにて公演も行う。 WEB・ITにおける人材不足問題の解決に際し初期段階での精度高いキャリアカウンセリング、採用支援の必要性を感じ、 手前の営業都合を優先しない「候補者、企業双方へ将来に渡り大きな価値提供」を目指し株式会社インフラトップ/マケキャンbyDMM.comに入社。
キャリア責任者を経て、現在は社長室にて事業推進を担当。2024年には、イギリス経営学を学びMBAを取得。
現代社会に求められる「筋の良いキャリア」を描くスキルとは?

ー 谷口さん、本日はどうぞ宜しくお願いいたします!まず始めに今までのご経歴や、マケキャンで現在どのような業務を担当されているかなど簡単に教えてください。
谷口:よろしくお願いします!
前職では、グローバルヘッドハンターとして国内外の転職支援を行う仕事をしていました。
CXOなど年収1,000万円を越えるようなハイクラスの転職支援を強みとしており、それこそ、マケキャンを卒業した方々が「いつか目指したい」とロールモデルになるような方々の転職支援を多数行ってきました。
マケキャン入社後は、キャリア責任者を経て、現在は社長室という部署にいます。
社長室は事業企画や推進など、経営・事業に関わるあらゆることを担う組織で、現在も多岐にわたるプロジェクトや業務に携わっています。
またイギリスの大学院で経営学を学び、MBA取得後はCMI(Chartered Management Institute)というイギリス王室勅許の経営やリーダーシップの育成・認定を行う専門機関資格を取得し、同機関の会員として引き続きキャリアに関して世界の先端学術を元に研究を行っております。
※日本ではあまり本格的ではありませんが、欧米ではキャリアの研究は経営学で盛んに研究されています。
わたしのこれまでのキャリアや人生の根幹にはずっと「キャリアの本質を追いかけたい、それを地図にのせてキャリアを支援したい」という思いがあり、それを実現すべく今でもキャリアの研究やノウハウの取得を継続的に行っています。
ー MBA取得おめでとうございます!早速ですが、ここ最近「キャリアコーチング」という言葉をよく耳にします。
谷口さんが考える「キャリアコーチング」の一般的な定義というのはどのようなものでしょうか?
谷口:私の個人的な見解も含まれますが、“自分自身で「こんなキャリアを作りたい」と思える状態を作り、自ら行動できるようにする“というのが、キャリアコーチングの目的だと捉えています。
とはいっても、実は「キャリアコーチング」という言葉そのものを厳密に定義したものって、論文などを探してもほとんど見当たらないんですよね。
なので、“キャリア”と“コーチング”をそれぞれで定義して、両者を組み合わせて考えるのが、今のところ最も良い解釈になるのではないかと考えています。
まず“キャリア”の語源は「轍(車の輪が通った跡)」という言葉からきていて、これは経歴や営みが連鎖して続いていくイメージを表していると捉えています。
そして“コーチング”は、自律的な学習や持続的な変化を促進するコミュニケーション手法と定義されています。
つまり、両者を組み合わせると「連続するキャリアにおいて自律的な学習と持続的な変化を促す手法」がキャリアコーチング、となるわけです。
そんなことを言われても難しいですよね(笑)
これを私なりに咀嚼して解釈すると、先ほど申し上げたような表現が今のところ最もしっくりきています。
ー なるほど。分かったようで分からないようで…改めて言語化してみると難しいですね(笑)一般的なキャリアコーチングの手法についてもお聞かせいただけますか?
谷口:一般的なキャリアコーチングというと、まずは自己分析から始まって、「理想の自分はどんな姿か?」をイメージし、そこから行動計画を立てていく流れが多い印象です。
もっと言えば、よく見られるコーチング手法の根幹には、「答えはあなたの中にありますよ」というスタンスが基本にあって、ひたすら傾聴しながらその人自身に寄り添って答えを引き出す、というイメージが強いんですよね。
ただ一方で、イギリスなどでは学術的な根拠に基づいてキャリアコーチングを定義づける取り組みが進んできています。
このようにその国のカルチャーなどによって定義や手法が少しずつ異なり、厳密に定義されているものではありません。
ー 国によっても捉え方や定義が異なるんですね。ところで、ここ最近キャリアコーチングへの関心が高まっているのはなぜなのでしょうか?
谷口:背景には、いまの日本の経済状況や社会環境が大きく関係していると思います。
たとえばGDPの成長率はいまや1%を下回り、“ゼロ成長社会”とも言われるほど先行きが不透明な時代になっています。
厳密に言うとマイナスばかりではなく、“プラマイゼロ”に近い状態なんですけど、それでも昔のバブル時代のように「どこに身を置こうと、勝手に経済が伸び続けて給料が上がり続ける」なんてことは、この時代に期待できません。
逆に言えば、いまは“どこに身を置くか”によって、自分の成長や働き方がプラスにもマイナスにも大きく振れる時代なんですよね。つまり、社会の時流に合わせてキャリアを変化させないと、いわゆる“詰んだ状態”になってしまうことすらある。
だからこそ、自分で“筋の良いキャリア”を考える力が必要になっていて、その一つの手段としてキャリアコーチングが注目を集めているんだと考えます。
じゃあ“筋の良さそうなキャリアをどうやって考えるのか?”が大事になってくるわけですが、それこそマケキャンでは、土台となる考え方をみなさんに持ってもらえるようなサポートを展開しています。
世界標準モデルを導入した完全独自のマケキャン流キャリア理論

ー ここからは谷口さんが開発した「マケキャン独自のキャリア論」についてお伺いしていきます。まず、一般的なキャリア理論とはどのような点が異なるのでしょうか?
谷口:私たちのカリキュラムは、世界の先端キャリア学術を元に設計しているので違いは色々ありますが、一例をあげると「自己発見型コーチングの限界」を踏まえて設計をしているということ。
先ほど申し上げた通り日本の一般的なキャリアコーチング理論だと傾聴と肯定を繰り返し「あなたの中に答えがあります」というスタンスが王道です。
つまり何度も自分の心に問い続ければ、いつかは1つの答えに辿り着きます、という考え方ですね。
もちろんそれ自体は間違ってはいないんですが、これだけだとその時に出てきた“答え”が果たして本当に“筋の良いもの”なのか、という疑問が残るんです。
たとえば、まだ経験が浅くて知識やスキルの“引き出し”が少ない人にとっては、自分の中から引き出せる答えが十分ではない可能性がありますし、経済的、社会的な制約を考慮していません。
「自分の中にあった答えが実は一直線にマズイ方向に行ってるかもしれない」ということもあり、それをフィードバックする術を持っていません。
そこが「自己発見型コーチング」の限界だと思っていて、マケキャンではその限界を踏まえて答えを「自分の中から見つけ出すだけ」というスタンスは取らないようにしています。
もう一つ大きな違いは、経済学的な視点を踏まえた設計になっているということ。
いまの世の中って、“自分がどれだけ競合優位性のあるスキルを身につけられるか”がすごく大事なのですが、この視点が、前述したいわゆる一般的なキャリアコーチング理論からは欠落していることが多くあります。
自分が市場において希少性高く模倣も代替も困難な存在になっているからこそ、仕事や信頼が集まり、結果的に経済的な安定や評価にもつながる。
キャリアを考える上でも「どうやって自分独自の強みを作り、そこを市場にあてはめていくのか?」という視点が不可欠なんです。※経済学と言っても難しい用語や数式は一切使わないので安心してください。
ー なるほど。つまり現代を生き延びるという視点で考えた時に、必ずしも自分自身で辿り着いた答えが筋の良いものではない可能性がある、と。
谷口:残念ながら大いにあると思います。
もちろん、自分が好きなことを仕事にできればきっと毎日楽しいと思いますし、それ自体は追い求めていきたい。
しかしそれで世の中に求められるポジションがとれたり、経済的に豊かで自由な暮らしができるか、というのは全く別の問題です。
我々の生きている世界でのキャリアには「パッション」と「合理性」という2つのテーマが、相反することなく両立して考える必要があります。
そこで、マケキャンでのカリキュラムでは、例えば認知心理学に基づいた、みなさんが普段内省することのない「無意識の認知システム」から自身の好きなことや本当にやりたいことを発見したり、さらに、経済学で用いるフレームワークを個人向けに落とし込んで、自分だけの“競争優位性(あなただけの強み)”をどう確立するかを具体化したり、社会学を使ったキャリア進展に必要なネットワークの仕組みなどをキャリアアドバイザーと面談していきながら少しずつ学んでいきます。
これは、海外では当たり前のようにキャリア論のベースとして取り入れられているんですが、日本ではまだ浸透していないんです。
だからといって海外のモデルをそのまま取り入れれば良いかというと、それではうまく行きません。
「日本独自のカルチャー」や「日本人独特の考え方」のようなものを無視しては浸透しないので、私たちはそこを両立させる工夫をしています。
言ってみれば、世界標準のキャリア学術をベースに、日本の文化や慣習をうまく組み合わせて結論が出せるように導いているんです。
少し長くなってしまいましたが、とにかく私が常々思っているのは「キャリアに今後一切迷いたくない人には、ぜひマケキャンのキャリアカリキュラムを試してみてほしい」ということです。
どういうキャリアを歩んでいくべきか?「キャリアを考える土台を作り、その上で自分の中の答えを探す」ことでキャリアの答えを導き出すことができるので、それを一緒に見つけませんか?というのが私が一番伝えたいメッセージですね。
ー 世界標準のモデルを日本にうまくローカライズさせたのがマケキャン独自のキャリア理論というわけなんですね!なぜそもそも、この理論を開発するに至ったのでしょうか?
谷口:シンプルに、「日本に自分が”受けたい”と感じるキャリアコーチングがなかったから」です(笑)
世の中に転職サービスはたくさんありますし、エージェントの方が話を聞いてくれるのはいいんですけど、その結果として導き出された“答え”が本当に正しいのかどうか、根拠が見えないまま進んでしまうことが多いじゃないですか。
私はそこにちょっと疑問を抱いていたんですよね。
そして自ら研究を進めていくうちに「じゃあ、こういうモデルがあったら自分も実践してみたいし、誰かの役にも立てるかもしれない」という思いで、いまの形へと行き着いた感じですね。
マケキャンは”一生キャリア形成に悩まない状態”を提供するサービス

ー これまで語っていただいた「マケキャン独自のキャリア理論」ですが、カリキュラムの中へどのようにして落とし込んでいるのでしょうか?
谷口:まず前提として、キャリアや経営学の最高峰とされる世界的な論文を約200本、さらに書籍を約100冊は読み込み、それを“誰でもわかるような形”にぎゅっと濃縮してまとめたのが、今のマケキャンのキャリア理論なんですよね。
どんなに優れた理論でも、専門用語が並ぶだけでは“伝わらない”し、受講生が「自分で使える」レベルまで落とし込まないと意味がありません。
だからこそ、私たちは分かりやすさを最優先にして、カリキュラムとして体系的に組み込み、キャリアアドバイザー全員が同じフォーマットでコーチングできるようにしているんです。
最終的に目指しているのは、受講生が卒業後にもこのモデルを自ら扱い、自分のキャリアを自律的に考えられるようにすること。そのための“土台作り”に力をいれています。
このキャリアカリキュラムの成果もあり、過去の卒業生のみなさんも「自身のキャリアはなぜ進展できたのか」を論理的に説明できる状態です。
「キャリア進展がなぜ起こったのか」を論理的に説明できるカリキュラムは日本では少ないのではないでしょうか。
ー 論文200本、書籍100冊…。その内容を短期間で取得できるというのはかなり大きなメリットですね!このキャリア理論における、これまでの実績はいかがでしょうか?
谷口:例えば、私たちのキャリア理論を活用して“意図的に年収1,000万円を突破”した受講生がいます。
その方はもともとお金にそこまで執着していたわけではなかったんですが、「より市場価値の高い人材になりビジネスのあらゆる側面で活躍したい」という思いをお持ちでした。
そこで、一緒に、今後とるべきポジショニング戦略や、活かすべき強みや能力などを考えた結果、会社や市場からどんどん評価されて昇給が重なり、今では家族を持ちつつ経済的にも豊かな生活を送っていらっしゃいます。
大事なのは、その方が「なぜそうなれたか?」を私たち自身が正しく論理的に説明できることであり、私たちの手法なら必ずそれができる、ということです。
「その方がたまたま優秀だったから」で片付けてしまっては、再現性のあるキャリアコーチングはできませんから。
ー なるほど、素晴らしい成果ですね。このような独自のキャリア理論があることによる、他スクールとの違いはどこにあると考えますか?
谷口:「キャリアに迷いたくないならマケキャン」というポジショニングを明確にとれることがマケキャンの強みだと考えています。
実際、転職そのものはあくまで手段であって、本当のゴールは“今抱えている将来への漠然とした不安を取り除き、自信を持って前に進める”という状態を手に入れることじゃないでしょうか。
「有名企業に転職できたからOK」という発想だけだと、また別のタイミングで必ず同じ不安に直面してしまって、その度に立ち止まってしまいます。
そのモヤモヤを根本から解消するためにも、たとえばWebマーケターという職種につくにしても「そもそもWebマーケターは市場価値を上げるのにふさわしい職種なのか?」とか「Webマーケティングの中でもどの領域なら自分の強みを活かせるのか?」という観点を踏まえたキャリア設計が重要になります。
マケキャンはそこを独自理論にもとづいて徹底的にサポートするので、結果的に“転職先できて、かつ転職先で自分の価値を発揮できる”状態を作れるんです。
これこそが、他のスクールと一番違う点かなと思いますね。
ー 「キャリアに迷いたくないならマケキャン」力強いコメントありがとうございます!それでは最後に、今後マーケターを目指されている方やマケキャンの受講を検討されている方などに向けて、応援メッセージをお願いします!
谷口:繰り返しになりますが、大事なことなのでもう一回言います。
「これ以上キャリアに迷いたくない!」と感じているのなら、ぜひマケキャンに来てください。
私たちはWebマーケティングのスキルや知識を教えるだけでなく、プログラム全体を通して“キャリアに迷わない”状態を提供している、と考えています。
もはや、Webマーケティングという職種自体も、1つの手段でしかないと捉えています。
ただ、Webマーケティングは市場も伸び続けていてこれからも需要が高まるので、そこに身を置くのはキャリア選択としても悪くない。むしろすごく有望な領域だと思います。
そういった意味でも、「今後一切迷うことなく、確かな道を進みたい」という方にはぜひマケキャンで学んでほしいですね。
ー 谷口さん、素敵なお話をありがとうございました!マケキャン受講を検討されている方々には、今後の長いキャリアも見据えて、ぜひ後悔のない決断をしてほしいですね!
マケキャンでは、「納得感ある転職」を実現するために、マケキャン独自の様々なサポートを行なっています。サービス内容に関するお問い合わせや、転職についての相談は、無料カウンセリングにて承っております。是非ご相談ください。